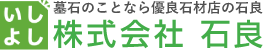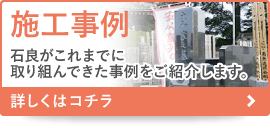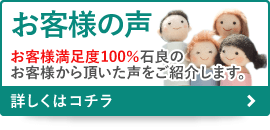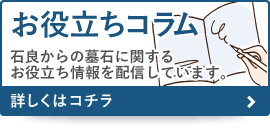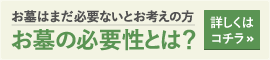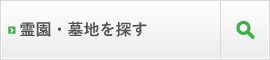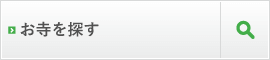日本の仏教行事の中でも、亡くなった方を供養するための「法要」は非常に重要な儀式です。しかし、法要とは具体的にどんなことをするのか、また「法事」とはどう違うのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。
法要は、故人の冥福を祈るための仏教的な儀式であり、遺族や親族が集まり、僧侶による読経を中心に行われます。本記事では、法要の意味や目的、基本的な流れ、法事との違いについて詳しくご紹介します。
目次
法要とは何か、その基本的な意味
法要とは、故人の冥福を祈り、成仏を願って仏教の作法に則って行われる供養のための宗教的儀式です。主にお寺の僧侶による読経が中心となり、その場に集まった家族や親族が共に祈りを捧げることで、故人との心のつながりを再確認します。
仏教における法要の位置づけ
仏教では、死後の魂が安らかに成仏するためには、遺族の供養が不可欠だとされています。法要はその代表的な行いであり、読経や焼香を通して、故人の魂に善い功徳を届けるとされます。
特に「初七日」「四十九日」「一周忌」などの節目に行われる法要は、故人の霊の行き先を定めるために重要な意味を持ちます。
法要の種類と時期について

法要は、故人が亡くなってからの経過に応じて複数の種類が存在し、それぞれの法要に特定の意味があります。法要のスケジュールは仏教の教義に基づいており、時期に合わせて適切に行うことが大切です。
主な法要の種類
- 初七日法要(亡くなった日を含めて7日目)
- 四十九日法要(7日ごとの供養を締めくくる最終法要)
- 百か日法要(死後100日目)
- 一周忌法要(満1年)
- 三回忌・七回忌・十三回忌などの年忌法要
特に「四十九日法要」は、故人の魂が現世を離れて次の世界へ旅立つ日とされており、親族や知人が集まり丁重に供養を行うのが一般的です。
法要の流れと行い方

法要には一定の流れがあり、僧侶による読経を中心に、参加者全員で祈りを捧げる形式が多く見られます。準備から当日の進行まで、事前に理解しておくとスムーズです。
一般的な法要の流れ
- 僧侶による読経
- 参列者による焼香
- 僧侶の法話(仏教に基づいたお話)
- 閉式・挨拶
- お斎(おとき)と呼ばれる食事会(任意)
法要は自宅や菩提寺、霊園の法要室、会館などで行われることが多く、開催場所によって必要な準備や服装も変わるため注意が必要です。
法要と法事の違いとは?

よく混同されがちな「法要」と「法事」ですが、実は意味に違いがあります。両者を正しく理解しておくことで、供養にふさわしい対応ができるようになります。
法要=宗教的な儀式、法事=法要を含む一連の行事
- 法要:僧侶による読経を中心とした宗教的な儀式
- 法事:法要に加え、その後の会食(お斎)や挨拶など、全体を含む行事
つまり、法要はあくまでも仏教的な供養の“核心部分”であり、法事はその法要を中心に据えた一連の社会的行事だと言えます。例えば、「一周忌の法事に出席する」という場合、法要だけでなく、その後の会食まで含めて招かれていることを意味します。
まとめ
この記事では、「法要とは何か」について、基本的な意味や種類、流れ、そして法事との違いまでを解説しました。
法要は、仏教において故人の冥福を祈る重要な儀式であり、四十九日や一周忌など節目ごとに丁重に行われます。また、法要は仏教儀式のことであり、法事はその全体行事を指すという違いも理解しておくと安心です。
故人とのつながりを大切にし、心を込めた供養を行うために、法要についての知識をしっかり身につけておきましょう。